どうも
同居を2回経験した。
30代のんき夫婦です。
同居を2回??
実親?義両親?
いえいえ、実母と2回です。
そして、多くの方が同居後20年後、30年後に向き合う問題
そう!介護についても経験しています。
このような経験から
同居を、少しでもストレスなく過ごす方法がわかりました。
今回はこの内容についてお伝えしたいと思います。
親との同居はどのようなイメージを持っていますか?
嫁姑問題、育児への干渉、介護問題、相続問題
全然いい情報が入ってきませんよね。
そんな中、いつの間にか
同居の流れになっている人も多いのではないかと思います。
「ムムッ」って感じがしませんか?
義母との同居は妻からしたら、とても気を使う日々だろうと思います。
サザエさんや、ちびまるこちゃんの家のように、
波平さんがマスオさんと毎晩晩酌するような
まるちゃんのおばあちゃんがお母さんと一緒にお茶をしているような
あのような
いい感じの同居は理想ではないでしょうか??
平和です。
現実は大変なことの連続です。
私たちは、母が病気になり一人暮らしが困難になり、
そんな同居は突然来ました。
同居のメリット、デメリットがいろいろ言われていますが、
正直
デメリットのほうが大半です。
しかし
私たちの同居は「今の所」とてもうまくいっています。
よい思い出もたくさんあります。
しかし
私たちが同居を経験し
同居の前に、同居をより気持ちよく続けるために必要なことは
事前に話し合う必要があるテーマに気づきました。
同居・介護を経験し
双方が同居を気持ちよく続けられるには、同居の前に何を話しておくのが重要かをお伝えします。
この記事がオススメの人
・同居について考えている人
・これから同居を考えている人
・今、同居をしている人
・兄弟・姉妹のいる人
同居を始める人必見!同居を始める前に話したほうがいいこと!

結論から言うと、この3つのテーマです!
・介護について
・相続について
・お墓について
さきにお伝えして置くと、この記事は今すぐに役立つとは限りません。
しかし、10年後、20年後に確実に意味をなしてきます。
その点をご承知ください。
介護について

同居をしたら介護をしないといけない??
同居=介護
同居≠介護
実はこれはとても曖昧になってませんか?
これを曖昧なままにすると、モヤモヤが溜まっていきます。
例えば
ちびまる子ちゃんで例えてみたいと思います。
まるちゃんも結婚し、旦那Bさんのご両親と同居したとします。
Bさんには兄Aさん(既婚)がいます。
子育てでは、食べさせたくないお菓子を姑は子供が喜ぶとばかりに欲しがれば、あげてしまいます。
せっかくおやつを控えて、食べない生活にしたかったのに、まるちゃんは「とほほ」とため息。
同居の時から遊びに行く時にも、舅、姑が顔がちらつきます。
数十年後、まるちゃんが旦那さんのご両親も高齢になります。
徐々に介護が必要になり、介護の日々に追われる、まるちゃん。
たまに義理姉のSNSを見ると、楽しそうな写真。
そんな義理姉は、なんのしがらみがないように見えて、
まるちゃんは「なんだかたのしそうだねぇ」と一人深いため息をつきます。
その後5年10年の長い介護を行い、2人とも亡くなったとします。
そのころまるちゃんは、介護をしている時には、長期の泊まりにも行きにくく予定を調整して旅行をします。
同居・介護の大変さは人それぞれですが、まるちゃんも大変だったと思います。
「なんで私がすべて介護しないといけなかったんだろう。兄がいるから、わたしゃてっきり、、、」と。
実の父ヒロシや母すみれを介護していないのに。
まるちゃんは一人部屋で思うのでした。
「とほほ、こんなことなら、同居の時にしっかり話して確認しておけばよかったよ」と。
相続につづく。キートン山田さん風に。
相続について

相続なんて、そんなお金もっていないから大丈夫!
そう思った方もいるかもしれませんが、相続問題は金額の大小ではありません。
遺産相続の問題は年々右肩あがりとのデータもあります。
少額の方が、相続問題を引き起こすという話も多く聞きます。
再び
ちびまる子ちゃんに例えて考えてみます。
まる子の旦那Bさんの兄Aさんは結婚してから一ヶ月に1回気分が向いたら、家族で遊びに来ます。
介護についてでも書いたように、長い同居と介護の末、ご両親が亡くなりました。
この時、兄Aさんが、「相続は半分だからね」と言いました。
さらに「途中から施設だったから大変じゃなかったでしょ」と言ってきました。
「なんてこというのよ!あんたぁ!」ってまるちゃんは心の中で怒ります。
介護をしたまるちゃん夫婦、介護しなかった兄Aさん家族。
もっというと
自分の両親ではない人を介護して過ごしたまるちゃんと
なんのしがらみもなく過ごした兄Aさんの嫁。
しかし、まるちゃんは「相続ちょうだいよ!半分ずつはおかしいよ」って思っても、
「これじゃ金の亡者だと思われる。」と何も言えません。主張もしにくい状況です。
相続欲しさに、介護をしたわけではないのに、、、
「あたしゃ、ほとほと疲れたよ」って口からこぼれます。
なんかなぁってなりませんか?
同居をするなら、最初からこの点についても話し合いをしておくと、良いと思います。
この話し合いの必要性を例えていうならば、
①バイトをするのに、時給1000円と提示されて1時間しっかり働いて1000円もらう。
②バイトをとりあえず1時間しっかり働く。そのあとでもらえる時給がわかる。
しかし、隣で55分遅れてきた人にも同じ時給がでる。
私だったら①を選びます。
同居する前に、話し合いをもたいないということは、②をしているようなものです。
しかし、現実は私たちは②になってしまいました。
そのため、私たちもまるちゃんと同じくモヤモヤしながら同居になります。
同居・介護あとの結果を明確にし、それをやるかやらないかの選択肢から選ぶことが大事ということです。
この方が確実に納得して同居生活を過ごすことができると思います。
私たちが介護と相続が関連していると思う理由はこういった点にあります。
そのためにも、相続についてもしっかりと話し合いをして納得し同居・介護に取り組む事が大事です。
墓・継ぐ継がない
これも、私が次男だから、ややこしくなるのだと思います。
家督相続がまだ根付いているのかいないのか。
同居していた親が亡くなって、親は先祖代々のお墓に入ります。
※我が家は、単純に父親のお墓の中です。
同居している母が、父のお墓の中に入って、
私たちは、新たにお墓を購入などをしてそこに入る?
兄たちは、父と母のお墓にはいる?
正直どうでもよいような、どうでもよくないような感じがしませんか?
では同居をしていて、墓参りなどは、私たち次男夫婦が取り仕切り、
母が亡くなってからは、兄夫婦が取り仕切る。
取り仕切りたいわけではないんです。
プロセスの問題です。
この点からも、介護、相続、墓・継ぐ継がないは関連しているテーマになると思います。
私たちの状況の説明
【親】
父は数年前に他界。
同居前の母の状況 は、母は家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、介護度では要支援でした。
サービスとしては、週1回の買い物同行、週2回の入浴介助の簡単な掃除。
調理もできず、買い物も自由にできず1日パンを1個しか食べないというような日もありました。
顕著に体重も減っていました。
このようなサービスをケアマネさんが調整してなんとか生活している状況でした。
【子供】
兄夫婦(子供2人)、 母の家まで兄の家から車で1時間半程度。2か月後に海外赴任が決まっていました。
次男夫婦 私たち(この時は子供2人)、家からバス・電車で1時間半程度(車所有していない)
いつ同居をはじめたか
1回目の同居は、なんとなく母が田舎から上京した後に始めました。
ほどほどに嫁姑問題、育児への干渉がありながらも1年一緒に過ごしました。
母が一人暮らしをすると言いだした時には、心配で止めましたが、母は引っ越して同居は終わりをとげます。
2回目はその数年後
母が病気になり、一人では暮らすことができなくなったタイミングで始まりました。
ヘルパーさんに入ってもらい、ガンガンサポートしてもらえれば、
寝たきりになろうが一人暮らしを継続できると思いますが、
そうする前に同居を判断しました。
よくある同居のタイミングは、結婚を機に、家を買う時、両親のどちらかが亡くなった時、
病気になった時などいろいろあると思います。
これらのタイミングでは、同居までに多少の期間があります。
同居までに今回あげた3つのテーマについて話し合いをすることが大事になってきます。
同居を始める前の夫婦の話
2回目の同居の前(同居3か月前)

今回は同居どうしようかな。
以前から何度か同居の話をしていて今回に至っているけど。。
病気の母を一人にできないもんね。
兄夫婦は私たちには同居はしないと言っても、母には伝えてないんだよね。
なんか別に悲しませる必要もないけど、それ言わないと母も期待するし、選択肢を考える上で変わっちゃうよね。
もう方向性を決めないと、バタバタと話をまとめる時間がなくなるね。
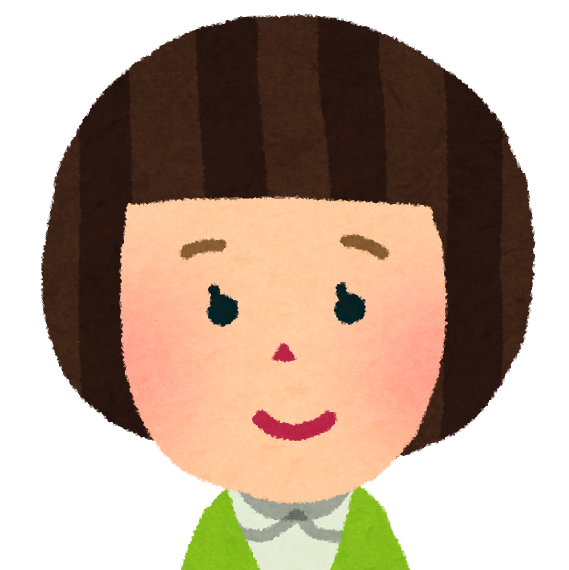
同居するしないの前にお母さんの意思も確認しないとね。
あとは私の両親の経験からも、兄弟間でいろいろな事を事前に話し合い確認した方がいいね。

母と兄夫婦と私たちで話し合いをしよう。
自分たちの意見もまとめておかないとね。
妻ちゃんには申し訳ないけど、母のこの先の選択肢の一つとして自分たちとの同居も、こちらから提示していいかな?
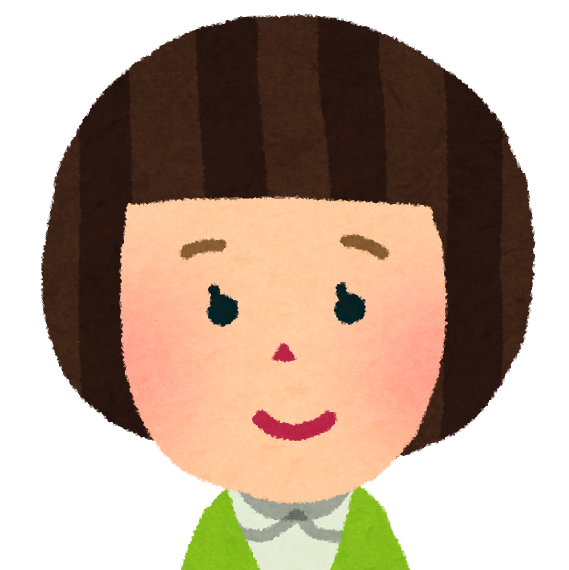
いいわよ。
おそらくお母さんも自分からは言いにくいだろうから、こちらからその選択肢もあることを言うのはいいわよ。
その中でお母さんの意思で選んでもらえるとことが大事だね。
古い考えかもしれませんが、
長男が、家を継ぐ(大した家ではないが)とか、墓を守るとか、墓はどこに入るとか、何か行事があった時には継いだ人が中心となり取り仕切るとか、親の面倒をみるとか、相続とか いろいろなことが繋がっていると思っていました。
この繋がっていることが、無用なトラブルなく物事をシンプルにするための慣習だと思っていました。
慣習なら慣習どおりにしますとみんなの共通認識が欲しかったのです。
これは、妻ちゃんの両親も同じような事案でとても嫌な経験し、
妻ちゃんの父の兄弟仲が悪くなったことがあるようです。
仲が良かった親族が、身内が亡くなったことで仲が悪くなるのは悲しいと。
ましてや私たち兄弟は、父が先に亡くなり、母も病気、残る兄弟の2人が仲が悪くなることはないよう。
そういったことを妻ちゃんは見ていたからこそ
無用なトラブルは起こしたくなかったという思いが強かったのです。
「仲良い親族だから、トラブルを起こさないから大丈夫。その時決めたらいい」なんていうのは、幻想。
仲良いのなら、無駄なトラブルの元を作らないために事前に話し合いができるはずです。
同居を始める前に母に伝えたこと
同居についての話し合いの前(同居3か月前)
私たちには、母は「一緒に同居したい」と話していた。
兄には「ギリギリやれるところまで一人で暮らしたい。その後は施設に入る」と話していた。
気持ちが揺れていたのかもしれないが、それでは困るのです。
母自身は介護経験がありませんでした。おそらくピンとこなかったのではないでしょうか。
また、兄が母に同居の意思がないことをしっかりと伝えていないことが、
話をこじれさせました。
この曖昧な返答が、このあとどれほど同居し介護者を苦労させるか。。

母は同居を選ばないとしたら、
すぐにでも施設に入るための資料請求、見学などの情報収集など施設に入る準備をしないといけない時期でした。しかし、それもできていませんでした。
まさに問題の先延ばしをしていました。
私たちだって正直に言うと同居をしたくしてするわけではないです。
母の場合は、同居=介護です。
私たちとしては、同居をしたほうがおそらく健康でいられる時期は少しでも伸ばせると思っていました。
またその在宅の期間に一人よりは家族で過ごすことが幸せなんじゃないかと思っての提案でした。
そして、母をお荷物のようにしたくなかったのです。
私たちはあくまでもこういう手助けはできるけど、必要ですか?
その手助けが必要と意思表示してくれるならば、しっかりと手伝いますということでした。
価値観は人それぞれ、母の意思が大事です。
おそらく、介護を始め、この部分がブレていると、
あれ? なんで介護してるんだっけ?
母親は施設がいいと言っていたのに、どうしてこんな苦労を買っているの??
私たちドM??これで母は幸せと思っていたのは私たちのエゴ??みたいなことになります。
そのため母に伝えたことは、
私たちは選択肢を出すけど、その決断を3者(母、兄夫婦、私たち夫婦)の中で、
意思をしっかりと伝えて欲しいと説明しました。
母:「わかった」と。
同居を始める時に兄夫婦に伝えたこと
話し合いの前(同居3か月前)
私たちと同居することになって。同居するということは介護をするということ。
介護するということに、私たちが思う関連したものの方針を確認したいということを伝えました。
内容としては
①家を継ぐ(大した家ではない)墓の管理
②親の介護について
③相続について
この点について
兄からは、「母の意思が大事だから。母のしたいようにしたらいいよ」と返答されました。
3者での話し合いの内容
母、私たち家族、兄家族での話し合いになりました。
兄からは、「母がもう少し、一人暮らしを頑張りたいならそれでいい」との話がありました。
この時点、兄は2か月後に海外赴任が決まっていました。
私、「それが現実的にもう厳しいから、この話をしている」「それだと、問題の先延ばしにしかならない」と伝えました。
母から 「一人暮らしをもう少し頑張って、その後、〇〇(次男:夫)のところにお世話になろうと思う」と話しがありました。
兄:「わかった」と。
妥協点ありありですが、これで、少なくても身近な身内での同意がとれたように思いました。
そして兄家族が海外赴任が2か月後に決まったので、全てを私たちが担う状況になったのでした。
それで他に決めたい内容はどう?と投げるもその場では決めることができませんでした。
兄に後日、同じ質問をすると「そんなに継ぎたいなら、継いだらいいじゃん」と返答されました。
だから そういうことじゃないじゃん!!!っと言い争いに。
そこで口論!
ただの意思確認だ!
そして継いだらいいじゃんということは、
例えて言うならば
①家を継ぐ(大した家ではない) → Aさん
②墓の管理 → Bさん
③親の介護 → Aさん
④相続 → Aさん Bさん
ってことじゃん。ちぐはぐなのがわからんかい!ってことなんだけど!
ちぐはぐでもいいから、どのように思っているか、ひとつひとつ教えてほしいと思っていました。
その中から、私たちの最善を選ぶだけがしたかったのです。
ここを、詰めれなかったのは私たちの反省点です。
その2か月後、兄は海外赴任にいきました。
その後、持ち越されたまま、兄から妻ちゃんへ「(次男:夫が)継ぐとか継がないとかこだわっているのはなに?」みたいな連絡がありました。
私たちが考えていた、関連したものをひとつひとつ整理したかったことが、
伝わっていなかったのがわかった瞬間でした。
そして継ぐ継がないの問題は、一番どうでもよい話です。笑
私たちのケースのまとめ
結論からいうと、
3つのテーマについて話を持ちかけたけど、詳細が決まらなかったという結果に終わり、
同居中モヤモヤしました。
モヤモヤの内容としては
母と兄の3つのテーマに対する回答がないことで、
介護がはじまっても、だれもこの介護を希望していないのでは?
という疑問を常に抱くようになります。
よかれと思って私たちにできることを伝えたはずでしたが、
「同居がいい」ではなく「同居でいい」みないな選び方になってしまった点です。
そんな消去法で選ばれても。。。
まとめ:同居を始める人必見!同居を始める前に話したほうがいいこと!
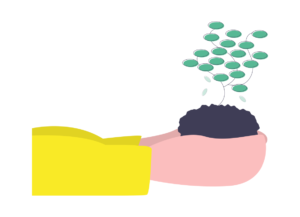
同居の時によく悩むのは、嫁姑問題、育児への干渉、プライバシーの少なさです。
たしかに今は、同居を望まない高齢者も多いと聞きます。
同居世帯は減っているというデータもあります。
参照元:内閣府 第1章 高齢化の状況
第2節 高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向(1) (2)子供との同居は減少している より
65歳以上の高齢者について子供との同居率をみると、昭和55(1980)年にほぼ7割であったものが、平成11(1999)年に50%を割り、26(2014)年には40.6%となっており、子どもとの同居の割合は大幅に減少している。一人暮らし又は夫婦のみの世帯については、ともに大幅に増加しており、昭和55(1980)年には合わせて3割弱であったものが、平成16(2004)年には過半数を超え、26(2014)年には55.4%まで増加している(図1-2-1-2)。
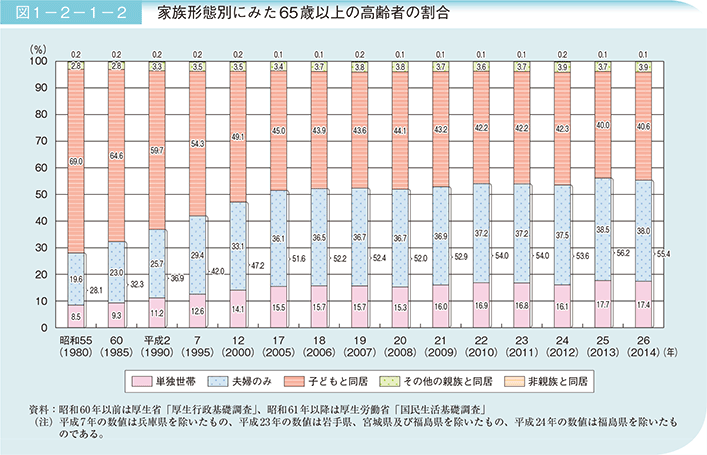
グラフからも同居をしている世帯が減っています。
私としては意外だったのですが、2014年ではありますが、まだ4割も同居している世帯がいます!
同志はいっぱいいます!
政府は、
今の日本の課題から
在宅での介護をすすめています。
両親が共働きをしないと回らないような状況のため、育児も課題になっています。
その打開策に、3世代同居をすすめています。
この育児と介護をマンパワーで補うということですが、その中心的役割を担う40代50代が数年後に
育児と介護のダブルケアになる可能性が高くなっています。
では私たち世帯は同居に何を求めているのでしょうか?
参照元:立法と調査 2019.10 三世代の同居・近居の現状と推進に向けた課題
図表3 (両)親と同居等する理由(上位2つ)
居住形態 | 理由(上位2つ) | 割合 | |
同居 | 自分の(両)親と同居している | 住居費や生活費が安くて済むから | 31.2% |
子育てを助けてもらえるから | 25.7% | ||
配偶者またはパートナーの(両) 親と同居している | 住居費や生活費が安くて済むから | 20.1% | |
子育てを助けてもらえるから | 19.2% | ||
近居 | 自分の(両)親と近居している | たまたま近くに住むことになったから | 52.0% |
子育てを助けてもらえるから | 25.6% | ||
配偶者またはパートナーの(両) 親と近居している | たまたま近くに住むことになったから | 54.6% | |
子育てを助けてもらえるから | 20.7% | ||
(出所)内閣府「少子化社会対策に関する意識調査報告書」を基に筆者作成
主に生活費と育児のサポートです。
しかし、舅、姑は同居をなぜしたがるのでしょうか?
舅、姑も若い時は、同居が嫌だったのではないでしょうか?
おそらく老後の不安だからではないでしょうか。
同居し数年経つと親は介護を期待し、私たちは悩むという構図ができあがります。
親は、「私は介護が必要になったら施設に入る」とよくいいます。
現実はそんなにシンプルではないです。
今回の3つのテーマなどは話しにくいテーマだと思います。
しかし
同居など、今後の方向性についての話は、健康なうちから早めに話しておくほうがいいと思います。
そしてできるだけ考えうる事柄に関しては、親族間の同意をとっておくことが大事だと思います。
また
介護される側、する側が、上記のデータのように、相手が何を求めているかを理解しながら同居についての話をすることにより、同居がうまく続けれると可能性が高まると思います。
ひとそれぞれですがいずれ人は歳をとり、介護が必要になり、亡くなります。
・介護について
・相続について
・お墓について
この3つは同居の形は違えど必要なテーマかと思います。
3世代もしくは2世代の同居がうまくいくよう、三方良しの方法があるはずです。
そのためには、当事者たちの中での正解を探すための話し合いを行う事が大事になります。
追記
結局3者で最後まで詰めた話はできなかったです。
この後、この決めなかった内容のことで、同居中大変モヤモヤしまくるということになる。
そして
今後、話し合わなかったことの結果がわかります。
どうなるやら。。。
とほほ やれやれ
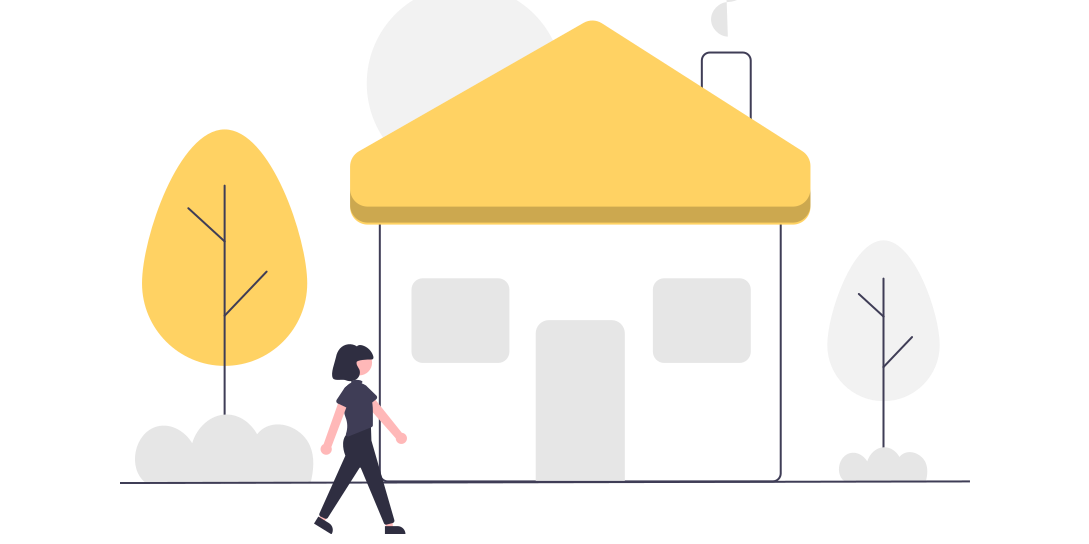


コメント