こんにちは
のんき夫婦です。
母が水分をなかなか飲んでくれません。
介護が必要な人が水分をとってくれなくて困ったことはありませんか?
今回は、母の体験を通して同じような悩みを持っている人にすこしでも力になれると思う話です。
この記事をオススメな人
・身内に水分を取ってくれない人がいる。
水分を摂りたがらなかった母が水分を摂るようになった5つの工夫!
母の様子から飲まなく乗った原因を探り
その後、飲むように働きかけた工夫をお伝えします。
母の様子 原因を探す
暑い夏の日
夜も熱帯夜のごとく寝苦しい日が続く中
冷蔵庫から麦茶をだして
大人も子供もゴクゴクと
いっぱい 飲み干すほど飲んでいました。
しかし
母は水分をほとんど飲みませんでして。
歳をとると、喉の渇きを感じにくくなり水分を取らなくなると言われています。
しかし、母はまだ60歳です。
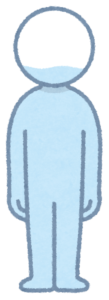
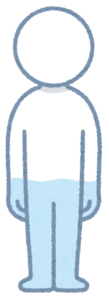
どうして飲まないの?と聞くと
「喉が乾かない」と返答がありました。
がんばって飲まないとと説明すると
「わかった」と言ってコップに口をつける程度で終えてしまいます。
「はあ!?」「今飲んだ??」と
場合によってはこういう流れで、言い争いになったりすることも幾度となく。。
お互いのためにと思っているのに口論になる。介護あるある。。
しつこく聞くと
「トイレに行くのが大変だから」と教えてくれました。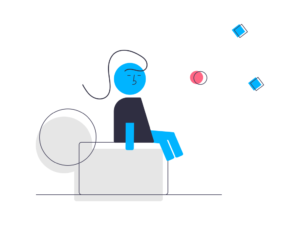
母は
なんとかトイレに一人で壁伝えに行っていました。
椅子から立ち上がり歩くのは徐々に不安定になっていったため、見守りを都度していました。
ダイニングからトイレまで数秒の距離。
ドタバタな長男5歳児のトイレでは最初から最後まで1分もかからずにでてくるが、母にとっては大イベントになっていたのです。
それで水分を控えていたのかとわかりました。
たしかに失敗したりしたあとなどは、その傾向が強くなっていました。
母なりに、失敗する→迷惑かける→トイレを減らす→飲む量を減らす
と工夫していたのだろうと思います。
私たちが考えた5つの工夫!
工夫は全部で5つあります。
工夫①:下着の工夫 パットを工夫
工夫②:飲み物の工夫 ゼリーを買う
工夫③:水分を取る環境の工夫 子供達と一緒に飲む
工夫④:トイレの声かけの工夫
工夫⑤:トイレの介助の工夫
工夫①:下着の工夫 パットを工夫
同居数ヶ月後の母は、トイレに間に合わず、少しの量の失敗をするのが月に1回あるかないか程度でした。
そのため、下着は介護用のものではなく普通の下着を使用していました。
少しでも安心できるように下着にパットを入れることにしました。
当初提案する時には、母のさみしい気持ち、嫌な気持ちがするのかと心配し言いにくかったが、
言ってみると特にそういったそぶりも見せず、了解してくれました。
いっぺんに介護用のパンツ(リハビリパンツ)にしなかったのは、少しずつ段階を経ていこうとおもったからです。
介護用パットもいろいろ種類があり、1回漏れても大丈夫な用、2回漏れても大丈夫な用、あとは下着にマジックテープみたいなので固定するタイプ、シールで固定するタイプなどあります。
母は、この頃はなんとかパット交換は自分でできたので、マジックテープで止めるタイプの割と薄いタイプのパットをチョイスしていました。
工夫②:飲み物の工夫 ゼリーを買う

病気の進行が、飲み込みにも影響が出始めていた。水分がやや飲み込みにくいということだった。そこで、飲み物をゼリーに変えた。
そうしたら、飲みやすかったようで、ゴクゴク飲むことができるようになった。
私たちは水分のような150mlゼリーを(パピコみたいな形)大量に買っていた。あとは、Qooというジュースゼリーも大量に買っていた。
今思えば、お茶でも水でもジュースでもゼラチンで固めてゼリーでも安上がりでよかったかなと。。
工夫③:水分を取る環境の工夫 時間を決める、子供達と一緒に飲む
飲んで欲しい気持ちが全面に出てしまうと、どうしても飲まされている感じになってしまいます。
ノルマになると母もつらいだろうなと。
そこで時間を決めて飲んでもらうようにしました。
リハビリ後、デイサービス後、お風呂後、食事時などに飲んでもらいました。
デイサービスのスタッフの人、ヘルパーさんにも協力してもらいながら、無理強いしない
程度に協力してもらいました。
その他は、飲むときの工夫をしたのが、孫と一緒に飲むということです。
ヘルパーさんにお風呂を入れてもらったあとは、孫たちもゼリー飲みたさに母の元にいき、
「おばあちゃんゼリーいい??」と聞いて「おばあちゃんも」と言い一緒に飲むという方法です。
孫に助けられる場面が多くあった。
工夫④:トイレの声かけの工夫
トイレのタイミングについては、母の尿意に任せていましたが、
のんびりした性格だからなのか
なぜか自分のトイレに行きたいと思うタイミングはギリギリでした。
そのため、タイミングをみて声をかけるようにしました。
工夫⑤:トイレの介助の工夫
自力で歩いていくのもリハビリと思い見守っていましたが、
リハビリよりもトイレで失敗しないように歩くのを少し介助しました。
トイレの中では、一人でズボンの上げ下げをしていたので、
ズボン着脱の動作がしやすいように、
ケアマネさんに伝え、サプライさんにトイレ用の手すり設置してもらいました。
私たちの家ではI字の棒をつけました。
これで立ち上がりや、ズボンの上げ下げ時寄りかかりながらできて、楽になったようでした。
そのため、トイレのために水分を我慢するということが少し減ったようでした。
水分を少しずつ取れるようになったことでのメリット
メリットは3つあります。
・脱水予防になる。
・排便コントロールがよくなった。
本当に大変な便秘だったようだ
健康な時には毎日1回はでる快便であったが
水分を気にしてからは、2日に1回、3日に1回、1週間に1回になっていた。
その時は本当に辛そうであった
・家族の心配のネタがひとつ減った
家族としても、水分を取らないのはとても心配でした。
また排便も出ないときは、つらそうで大変でした。こういったものが解消されると家族としても安心します。
まとめ:水分を摂りたがらなかった母が水分を摂るようになった5つの工夫!
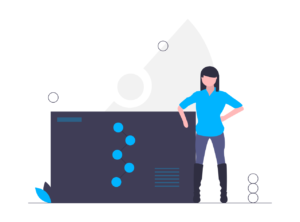
工夫①:下着の工夫 パットを工夫
工夫②:飲み物の工夫 ゼリーを買う
工夫③:水分を取る環境の工夫 子供達と一緒に飲む
工夫④:トイレの声かけの工夫
工夫⑤:トイレの介助の工夫
これらの工夫をとることで、少しでも元気な方が増えるとうれしいです。



コメント